このブログでは、NHKの英語ラジオ番組「Enjoy Simple English(エンジョイ・シンプル・イングリッシュ)」の内容をもとに、
- 日本語訳
- チャンク&単語解説
- 英語での要約
を毎日更新しています。
毎週金曜日は「小泉八雲が愛した日本の民話”Stories Lafcadio Hearn Collected around Japan”」です。明治時代に来日したラフカディオ・ハーンは妻・セツと出会い小泉八雲と名乗った。2人で紡ぎ世界に広めた日本各地の怪談・奇談を紹介しています。
本日のStories Lafcadio Hearn Collected around Japanのストーリーは「Of a Mirror and a Bell」です。
「聞き取れなかったところを確認したい」
「ストーリーを理解してからもう一度聞きたい」
そんな方の学習補助として活用していただけたら嬉しいです。
また、チャンク&単語解説は、日常会話で役立つものやESEで頻繁に出てくるものをピックアップして解説しています。隙間時間の学び直し等にも有効に活用できると思います。
ではさっそく、今日の内容を見ていきましょう!

本日のストーリー:日本語訳
1ページ目
800年前、遠江地方の無間山の僧たちは、女性たちに青銅の鏡を寄付するように頼みました。彼らはその鏡を溶かして、お寺に大きな鐘を作ろうとしていたのです。
ある若い女性が鏡をお寺に差し出しましたが、後になってその選択を後悔しました。彼女は心の中でこう思いました。
「鏡は女性の魂だということわざがある。私は、自分の人生の一部を愚かにも差し出してしまったような気がする。」
鐘を作る際、どうしても溶けない鏡が一つありました。その鏡には、彼女のわがままな魂が残っていて、炎の中でも固く冷たいままだったのです。
すぐに誰の鏡かが知れ渡り、彼女は恥じて自ら命を絶ちました。そして手紙を残しました。
「私は幽霊となり、鐘を鳴らして壊した者に大きな富を授けます。」
その鐘がお寺に掛けられると、多くの人が鳴らしにやってきました。昼も夜も、毎日のように鐘を鳴らし続けました。しかし鐘は決して壊れませんでした。僧たちはその音にうんざりし、鐘を…
2ページ目
…沼へと転がしました。鐘は姿を消し、「無間鐘(むげんがね)」という伝説になりました。
鐘が沼に転がされてからは、実際に鳴らすことも壊すこともできなくなりました。そこで人々は、別の物を鐘に見立てて使い、それを壊せば富が得られると願いました。これは日本の「なぞらえる」という考え方に由来します。つまり、何かを別の物に見立てて魔法のような結果を得ようとするのです。
3ページ目
そのような女性の一人が「梅ヶ枝(うめがえ)」でした。彼女の恋人は平家の武士で、ある日、急にお金が必要になりました。梅ヶ枝は無間鐘の伝承を思い出し、青銅製の鍋を鐘と見立てて、それを叩き壊しました。そして壊れると同時に、こう叫びました。
「黄金300両が欲しい!」
4ページ目
同じ宿に泊まっていた客がその話を聞き、梅ヶ枝に金を与えました。
梅ヶ枝と無間鐘の話は広まり、多くの人が真似をしようとしました。中でも、あるとても貧しい農夫が、泥で作った鐘で同じことを試しました。彼はお金を使い果たして貧乏になっていたのです。その鐘を壊したとき、白い衣をまとった女性の幽霊が地面から現れ、こう言いました。
「あなたの願い、聞こえました。この壺をお取りなさい。」
5ページ目
そして彼女は、ふた付きの壺を渡して姿を消しました。農夫は喜び勇んで家に帰り、妻にその朗報を伝えました。2人で壺を開けると、それは中身でいっぱいでした。
…中に何が入っていたかは、ちょっとお教えできません。
日常生活で使えるチャンク&単語解説
ここでは日常生活で使えるチャンク(言葉のひとまとまり)や単語の解説をします。
チャンク&単語帳
以下のチャンクや単語をタップすると、日本語訳が出てくるので、訳を見ずに意味がわかるか挑戦してみてください!
僧侶
寄付する
〜を溶かす
〜を公開する
愚かにも
絶対に
恥じて
富、財産
沼
緊急に
宿屋、旅館
チャンクPickUP-1
She left behind a letter.
(日本語訳)彼女は手紙を残しました。
構成パーツの解説
上記文章のうち、left behind a letterの部分を解説します。
| パーツ | 意味 | 機能 |
| left | 「残した」「去った」(動詞 leave の過去形) | 主動詞(動作) |
| behind | 「後に」「置き去りにして」 | 副詞:場所を表す(”どこに” 残したのか) |
| a letter | 「メモ」「手紙」 | 目的語:何を残したか |
💡「left behind」でひとまとまりの動作「置いていった」「残していった」という意味になります。
“left”=「左」や “behind”=「後ろ」と覚えていると混乱しやすいですが、ここでは「(場所に)残した」という動詞句です。
応用表現
このチャンクは言葉を入れ替えることで、いろいろ応用が利きます。
– She left behind a message before leaving the house.
(彼女は家を出る前にメッセージを残しました。)
– The teacher left behind a legacy of kindness and wisdom.
(その先生は、親切さと知恵という遺産を残しました。)
– He disappeared and left behind nothing.
(彼は姿を消し、何も残しませんでした。)

チャンクPickUP-2
Then she handed him a covered jar and disappeared.
(日本語訳)そして彼女は、ふた付きの壺を渡して姿を消しました。
構成パーツの解説
上記文章のうち、handed him a covered jarの部分を解説します。
| パーツ | 意味 | 機能 |
| handed | 「手渡した」(動詞 hand の過去形) | 主動詞(動作) |
| him | 「彼に」(人称代名詞の目的格) | 間接目的語(誰に手渡したか) |
| a covered jar | 「ふた付きの瓶」「ふた付きの壺」 | 直接目的語(何を手渡したか) |
💡ここでの hand は「手」という名詞ではなく、「手渡す」という動詞です。
これは英語でよくある「名詞→動詞化」パターンのひとつ。
使うときのポイント・注意点
- “hand + 人 + 物” の語順が基本
👉 相手が先、モノが後
(例:hand me the book.) - “give” よりも丁寧な印象や直接的な動作のニュアンス
(実際に“手で渡す”ことを強調) - ビジネスや接客でも自然に使える
(例:Let me hand you the menu.)
応用表現
– After the workout, I handed her a towel.
(トレーニングの後、私は彼女にタオルを渡しました。)
– I handed in the report just before the deadline.
(締切の直前にレポートを提出しました。)
– She handed over the keys to the new tenant.
(彼女は新しい住人に鍵を引き渡しました。)

She handed over the keys to the new tenant.
この文章のみ、「hand + 人 + 物」ではなく、物 + 人の順になっています。
実は、これは「hand」と「hand over」という言葉の使い方の違いが関係しています。
「hand」と「hand over」の違い
hand(単なる「手渡す」)
- 「hand 人 モノ」の順番
- 気軽な会話でよく使います
✅ 例文:
I handed her a towel.(彼女にタオルを渡した)
hand over(「正式に引き渡す」)
- 「hand over モノ to 人」の順番
- 公的な場面・ビジネス・引き継ぎなどに使われます
✅ 例文:
She handed over the keys to the new tenant.(彼女は新しい住人に鍵を引き渡した)
ポイントまとめ
| 表現 | 語順 | 使う場面 |
| hand | hand + 人 + モノ | 会話、日常の動作 |
| hand over | hand over + モノ + to + 人 | 引き継ぎ、ビジネス、正式なやりとり |
ちょっとした語順の違いですが、ネイティブはしっかり使い分けています。
「hand」=気軽に、「hand over」=ちょっとかしこまって、と覚えておくと自然な表現に近づけますよ!
関係代名詞の文章をPickUP

Enjoy Simple Englishでは関係代名詞を用いた長い一文がよく出てきます。そこで、ストーリーに出てきた関係代名詞を用いた文の構造や意味などをみていくことで、関係代名詞に強くなって、長文読解への抵抗をなくしましょう!
今回の一文
“I will become a ghost and give great wealth to the person who breaks the bell by ringing it.”
(日本語訳) 私は幽霊となり、鐘を鳴らして壊した者に大きな富を授けます。
構成パーツの解説
| パーツ | 解説 |
| the person | 「人」を示す先行詞(=誰に与えるか) |
| who | 関係代名詞(主格):「人」を説明する役割 |
| breaks the bell by ringing it | 関係詞節:どんな人かの説明「鐘を鳴らして壊す人」 |
今回使われている関係代名詞は、whoです。
💡 who は「the person」にかかっています。つまり、「鐘を鳴らして壊す人」という具体的な条件をつけて、「その人に富を与える」と言っているわけです。
- 「人」について追加情報を加えたいときに、who + 動詞 の形で説明する。
- who の後ろは普通の文と同じ語順(S + V)。
✅ よくある形:
- the person who helped me
- the student who answered the question
- the woman who lives next door
🔍 応用表現
- I’ll give this to the person who finishes first.
(最初に終わった人にこれをあげます。) - She married the man who saved her life.
(彼女は命を救ってくれた男性と結婚しました。) - We’re waiting for the guest who hasn’t arrived yet.
(私たちはまだ到着していないお客様を待っています。)
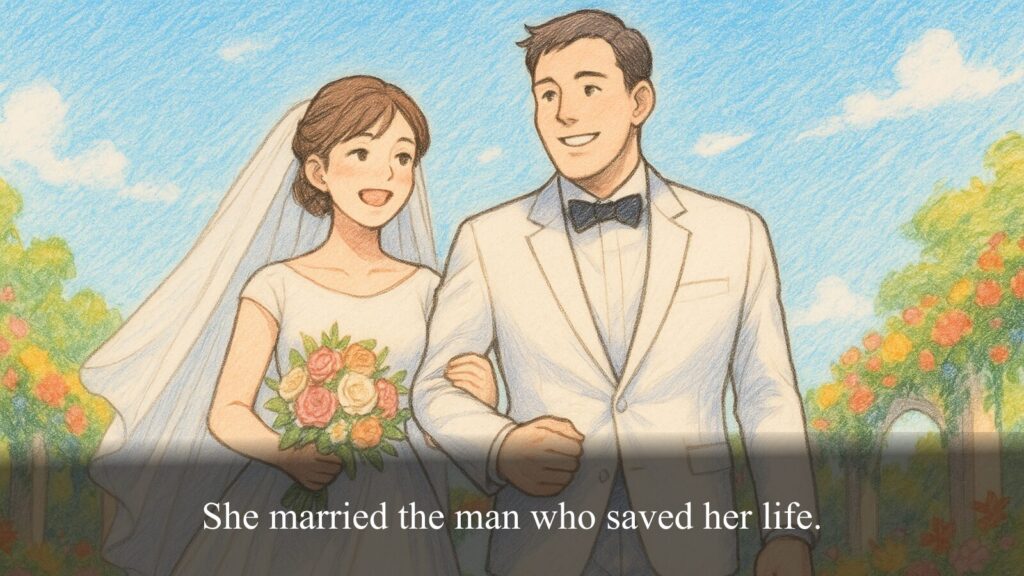
本日の記事の要約
今回の記事をAIが要約しました。ぜひリーディング練習にご利用ください!
要約 日本語訳:
遠い昔、遠江の国で、ある女性が寺の鐘を鋳造するために、自分の青銅の鏡を差し出しました。しかし後になってそのことを後悔しました。彼女の強い思いが鏡を溶かすことを妨げたのです。恥じ入った彼女は命を絶ち、「この鐘を鳴らして壊すことができた者には、自分の霊が報いを与えるだろう」という内容の書き置きを残しました。
しかし鐘は決して壊れることはなく、僧たちは鐘を沼に投げ捨てました。これが「無間の鐘」の伝説の始まりです。
後に、人々は「なぞらえ(なぞらえる)」の考えに従い、他の物を壊すことで富を得ようとしました。ある女性・梅ヶ枝(うめがえ)はそれに成功し、人々に希望を与えました。ある貧しい農夫も泥で作った鐘を壊したところ、幽霊から不思議な壺を授かりました。
今週のESEチャンク解説まとめ記事のご紹介
毎日の放送を追いかけている方も、ちょっと復習したい方も必見です!
今週の放送でピックアップしたチャンクをまとめて解説した【週末まとめ記事】を公開しています。このまとめ記事では、ESEの内容を思い出しながら、日々の英語学習に役立つ重要なチャンクを一気に振り返ることができます。
「チャンクをしっかり覚えたい」「英語表現力を高めたい」「1週間分を効率よく復習したい」という方には特におすすめです。再放送のタイミングでの復習や、苦手なチャンクの再確認にも便利ですので、ぜひチェックしてみてくださいね。
ESEの放送について
NHKのラジオ番組「Enjoy Simple English(ESE)」は、月曜〜金曜の毎朝6:00〜6:05(再放送あり)に、NHKラジオ第2で放送されています。
※最新の放送スケジュールや放送内容の詳細は、NHKの公式サイトをご確認ください。
👉 NHK Enjoy Simple English 公式ページ(外部リンク)
また、聞き逃してしまった場合も、「NHKゴガク」サイトや「らじる★らじる」アプリを使えば、放送から1週間以内であれば何度でも聞き直すことができます。
番組の内容をより深く理解したい方には、公式テキストの利用もおすすめです。
テキストには、毎日の英文スクリプトや語彙リストが掲載されており、学習効果を高めるのに非常に役立ちます。
📘 テキストは全国の書店や、Amazon・楽天ブックスなどのオンライン書店でも購入可能です。

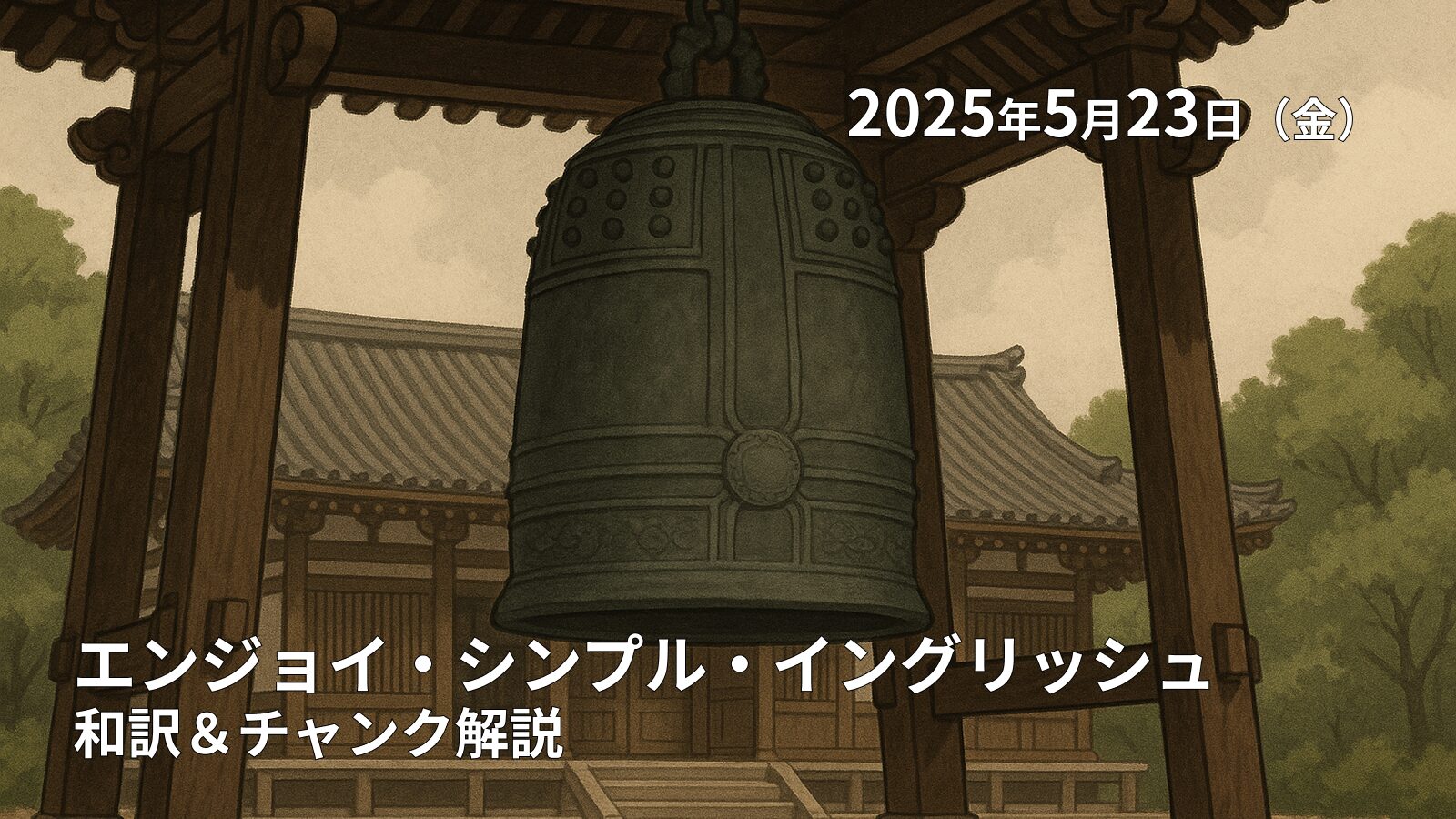



コメント