このブログでは、NHKの英語ラジオ番組「Enjoy Simple English」の内容をもとに、
- 本文和訳
- チャンク&単語解説
- 英語での要約
を毎日更新しています。
10月度からは、これまでの内容と異なり、2021年4月に放送されたものの再放送になります。
毎週水曜日は「世界の偉人伝”Heroes and Giants”」です。日本を、世界を動かした偉人たちの誰もが知るその偉業を、ちょっと意外なその素顔を、英語で味わうことができます。
本日のHeroes and Giantsのストーリーは「Bob Dylan ~ A Nobel Poet ~」です。
「聞き取れなかったところを確認したい」
「ストーリーを理解してからもう一度聞きたい」
そんな方の学習補助として活用していただけたら嬉しいです。
また、チャンク&単語解説は、日常会話で役立つものやESEで頻繁に出てくるものをピックアップして解説しています。隙間時間の学び直し等にも有効に活用できると思います。
ではさっそく、今日の内容を見ていきましょう!
Bob Dylan ~ A Nobel Poet ~(ボブ・ディラン 〜 ノーベル賞の詩人 〜):和訳
1ページ目
アメリカの歌手ボブ・ディランは1941年、米国北部に生まれた。1962年にファーストアルバムを発表し、たちまち人気を得た。1964年までには年間およそ200本のコンサートを行っていた。今日ではディランは70歳を超えているが、今も世界をツアーしている。50年以上にわたり、多くの人々に愛され、尊敬されてきた。2016年、ディランはノーベル文学賞を受賞した。
2ページ目
「偉大なアメリカ歌曲の伝統の中に新しい詩的表現を創出したことに対して」。つまりそれは、ブルースのような古い様式を取り入れ、それらを自分のスタイルへと作り変えたという意味である。こうした変化は、最初は人々にとって理解しにくいこともあった。しかし人々は、ディランの歌詞を自分の人生に重ね合わせ、その歌は彼らにとって大切なものになっていった。ヒット曲「Blowin’ in the Wind(風に吹かれて)」で、ディランはこう歌う。
The answer, my friend, is blowin’ in the wind
(答えはね、友よ、風に吹かれている。)
The answer is blowin’ in the wind
(答えは風に吹かれている。)
— “Blowin’ in the Wind”
人々はときどき、この歌が何を意味するのか彼に尋ねる。彼は、本やテレビ番組、人と話すことで答えが見つかるわけではないと説明する。答えは「風に吹かれている」のだ。ディランの歌はすべて反戦のフォークソングだと考える人もいるが、そうした歌を書いたのは1960年代のことだ。その後は、自分の感情や、ほかの人々が経験したことについて書いた。彼は教会音楽からパンクロックまで、実にさまざまなタイプの音楽に挑戦した。ときにはメディアや、さらにはファンでさえも、彼の音楽を悪く言うことがあった。
3ページ目
しかしディランは自分にふさわしい音楽のかたちを探し続けた。彼は「音楽の中に自分の居場所を見つけたかった」と語っている。ディランにとって、曲づくりではいつも言葉が先に来た。友人たちはこう語る。「彼はツアー中でもレコーディング中でも、タイプライターに向かって歌を書いていた」。音楽を書くことは彼の仕事ではない。それは彼の人生だ。ディランが曲を書くときは、いつもまず言葉を書き、それから音楽を加える。1965年のヒット曲「Like a Rolling Stone(転がる石のように)」のレコーディングは、その作り方を物語っている。スタジオでディランは、どんな音楽を録るつもりなのかを演奏者たちに伝えなかった。彼はいきなりマイクに向かって歌い始め、ミュージシャンたちは最善を尽くして彼に合わせて演奏しなければならなかった。
How does it feel
(どんな気分だい?)
To be on your own
(ひとりきりでいるのは。)
With no direction home
(帰るべき道しるべもなく。)
Like a complete unknown
(完全な見知らぬ者のように。)
Like a rolling stone?
(転がる石にように?)
— “Like a Rolling Stone”
ディランは曲づくりの計画を誰とも共有しない。しかし彼の書く歌は多くの人々に愛され、その歌は彼らの人生の一部になっていく。
日常生活で使えるチャンク&単語解説
ここでは日常生活で使えるチャンク(言葉のひとまとまり)や単語の解説をします。
チャンク&単語帳
以下のチャンクや単語をタップすると、日本語訳が出てくるので、訳を見ずに意味がわかるか挑戦してみてください!
詩人
基本的に、要するに
〜を…になぞらえる
無名の人

チャンクPickUP
These changes were sometimes difficult for people to understand at first.
(日本語訳)これらの変化は、最初のうちは、人々にとって理解するのがときどき難しかった。
構成パーツの解説
| パーツ | 意味 | 機能 | 補足 |
|---|---|---|---|
| These changes | これらの変化 | 主語 | 複数主語 |
| were sometimes difficult | ときどき難しかった | 述語(評価) | sometimes が頻度の緩和 |
| for people | 人々にとって | 評価の対象 | 「誰にとって難しいか」を示す |
| to understand | 理解することが | 不定詞(難しさの中身) | be difficult for 人 to V の型 |
| at first | 最初は | 時間副詞 | 期間限定(後には改善) |
be difficult for 人 to + 動詞は、「(人)にとって〜するのが難しい」という評価を客観的・丁寧に述べることができ、状況説明や配慮の表明に非常に使いやすいチャンクです。主語には「難しさの対象(物・事)」を置き、for + 人 で「誰にとって」を示し、to + 動詞 で「何をするのが」を具体化します。口語で少し砕くなら hard for 人 to V、やや前向きに言いたいなら challenging for 人 to V と言い換えられます。
ビジネスや観光案内では、断定を避けたいときに sometimes / a bit / at first / can be を添えると角が立たず、「最初は難しいが慣れる」という含みを持たせられます(It can be a bit difficult for visitors to navigate at first.)。
日常会話への応用
– It’s difficult for tourists to find trash bins in this area.
(この辺りでは、観光客にはゴミ箱を見つけるのが難しいんです。)
– I find it difficult to explain this in Japanese, but I’ll try.
(これを日本語で説明するのは難しいと感じますが、やってみます。)
PickUP長文読解
Enjoy Simple Englishでは関係代名詞等を用いた長い一文がよく出てきます。そこで、ストーリーに出てきた長文の構造や意味などを確認する中で、関係代名詞などの構文に強くなって、長文読解への抵抗をなくしましょう!
今回の一文
“In 2016, Dylan won the Nobel Prize for Literature “for having created new poetic expressions within the great American song tradition.””
(日本語訳)2016年、ディランはノーベル文学賞を受賞した。理由は「偉大なアメリカ歌曲の伝統の内において、新しい詩的表現を創出したこと」である。
構成パーツの解説
| パーツ | 意味 | 機能 | 補足 |
|---|---|---|---|
| In 2016, | 2016年に | 時間状況 | 文頭に置いて時を提示 |
| Dylan | ディランは | 主語 | 固有名詞 |
| won the Nobel Prize for Literature | ノーベル文学賞を受賞した | 述部 | 「for Literature」で部門(文学賞)を特定 |
| “for having created … tradition.” | 「…のゆえに」 | 受賞理由(引用) | ノーベル財団の公式表現を引用。文法的には for + 動名詞句 |
| having created | 創出したことにより | 完了分詞(前時性) | = because he had created の圧縮形 |
| new poetic expressions | 新しい詩的表現 | 目的語 | expressions=表現(複数) |
| within the great American song tradition | 偉大なアメリカ歌曲の伝統の内部で | 前置詞句(範囲・枠) | within=「~の内部で/内側で」→「伝統の枠内で」 |
読解のポイント
“for having created …” は「過去に創出したから」
引用内の for は「〜のゆえに/〜が理由で」。続く having created は完了分詞で、「(受賞時点より前に)創出していた」という前時性を表します。平叙に直せば for having created = because he had created。単に for creating でも意味は通じますが、having + p.p. は「すでに成し遂げていたこと」を丁寧に示す、アワード文言らしい格調のある書き方です。
“within” は「枠内の革新」を示すキーワード
within the great American song tradition は「偉大なアメリカ歌曲の伝統という枠組みの内側で」という意味。within は in よりも「内側/範囲の中」というニュアンスが強く、「伝統を壊して外へ出た」のではなく、伝統の内部で新しさを生み出したことを評価している、と解釈できます。
名詞句をまとめて読む:new poetic expressions
new poetic expressions は「新しい+詩的な+表現(複数)」のまとまり。poetic は詩そのものに限らず、「比喩・音韻・リズムなど詩的性質を備えた」という広い意味で、歌詞言語の革新を指しています。

本日の記事の要約
今回の記事をAIが要約しました。ぜひリーディング練習にご利用ください!
要約 日本語訳:
1941年生まれのボブ・ディランは、1962年に最初のアルバムを発表してすぐに人気となり、1964年には年間200本の公演を行った。2016年には、アメリカ歌曲の伝統に新しい詩的表現を生み出したとしてノーベル文学賞を受賞した。彼はブルースなどの古い様式を自分流に作り替え、歌詞は人々の人生に響いた。『風に吹かれて』は「答えは風の中にある」と歌う。彼はまず言葉を書き、その後に音楽を加える。
先週のESEチャンク解説まとめ記事のご紹介
毎日の放送を追いかけている方も、ちょっと復習したい方も必見です!
先週の放送でピックアップしたチャンクをまとめて解説した【週末まとめ記事】を公開しています。このまとめ記事では、ESEの内容を思い出しながら、日々の英語学習に役立つ重要なチャンクを一気に振り返ることができます。
「チャンクをしっかり覚えたい」「英語表現力を高めたい」「1週間分を効率よく復習したい」という方には特におすすめです。再放送のタイミングでの復習や、苦手なチャンクの再確認にも便利ですので、ぜひチェックしてみてくださいね。
ESEの放送について
NHKのラジオ番組「Enjoy Simple English(ESE)」は、月曜〜金曜の毎朝6:00〜6:05(再放送あり)に、NHKラジオ第2で放送されています。
※最新の放送スケジュールや放送内容の詳細は、NHKの公式サイトをご確認ください。
👉 NHK Enjoy Simple English 公式ページ(外部リンク)
また、聞き逃してしまった場合も、「NHKゴガク」サイトや「らじる★らじる」アプリを使えば、放送から1週間以内であれば何度でも聞き直すことができます。
番組の内容をより深く理解したい方には、公式テキストの利用もおすすめです。
テキストには、毎日の英文スクリプトや語彙リストが掲載されており、学習効果を高めるのに非常に役立ちます。
📘 テキストは全国の書店や、Amazon・楽天ブックスなどのオンライン書店でも購入可能です。
 | NHKラジオ エンジョイ・シンプル・イングリッシュ 2025年10月号[雑誌]【電子書籍】 価格:650円 |
 | ラジオ エンジョイ・シンプル・イングリッシュ 2025年10月号 価格:690円 |

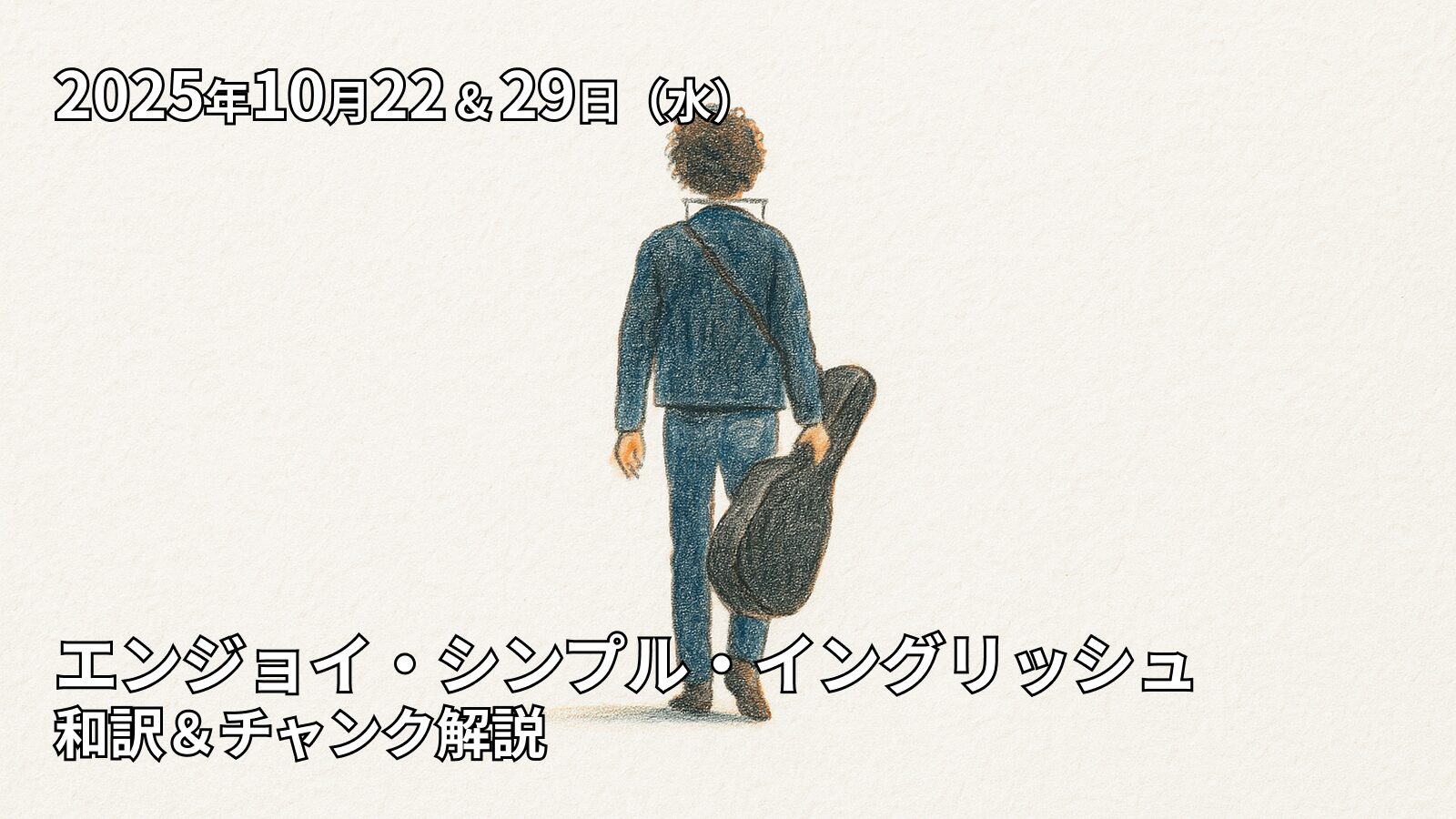



コメント